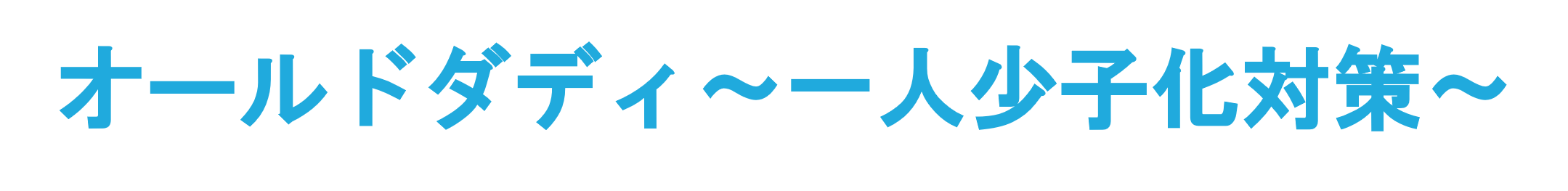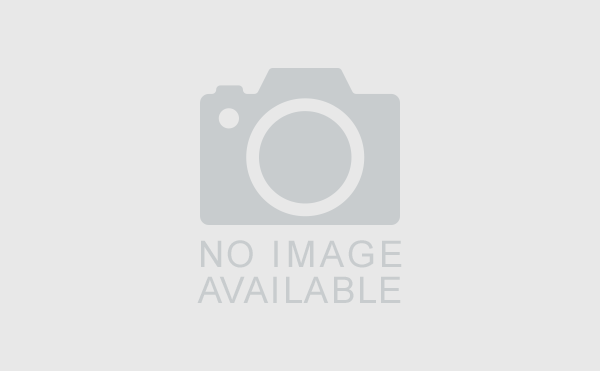妊娠を目指す前に知っておきたい感染症検査 ~安心のはじまりは検査から~
はじめに
妊娠を考え始めると、多くの方が食事や運動、生活習慣の見直しを始めます。しかし「感染症検査」まで意識できている方は意外と少ないかもしれません。
感染症の中には、自覚症状がないまま進行し、不妊症や流産、さらには胎児の先天異常につながるものも存在します。特に妊娠初期は胎児の臓器が形成される大切な時期で、この時期に感染すると回避が難しいケースもあります。
この記事では、妊娠前に受けておくべき感染症検査の種類や重要性、検査後の対応、パートナーと一緒に取り組むべき理由などを詳しく解説します。
1. 妊娠前に感染症検査をする意義
胎児への影響を防ぐ
HIVやB型肝炎、梅毒などの感染症は、母子感染により新生児に重篤な健康被害を与える可能性があります。母子感染は妊娠中だけでなく、出産時や授乳時にも起こり得ます。妊娠前に感染の有無を知ることで、出産方法や母乳育児の可否など、母子感染を防ぐ選択肢を取ることができます。
早期発見による対応
クラミジアや淋菌は放置すると骨盤内炎症性疾患(PID)を引き起こし、不妊症や子宮外妊娠のリスクを高めます。実際、イギリスでは、クラミジア感染が見逃され、妊娠18週で胎児を失った事例も報告されています。日本でも性感染症の無症状感染は少なくなく、「症状がない=大丈夫」ではありません。
妊娠準備の一環
風疹や水痘など、予防接種で防げる感染症もあります。抗体がないと判明すれば、妊娠前に接種して免疫を獲得できます。妊娠後は接種できないワクチンも多いため、事前準備が不可欠です。
2. 主な感染症検査の種類と意義
HIV
未発症でも数年後に免疫機能が低下し、重篤な感染症にかかりやすくなります。妊娠前に発見できれば抗ウイルス薬治療で母子感染をほぼ防げます。性交渉の経験がある人は一度は検査を受けるべきです。感染が分かった場合は専門医と連携して出産計画を立てます。
B型肝炎(HBV)
慢性化すると肝硬変や肝がんの原因になります。母子感染を防ぐため、感染がわかった場合は出産直後のワクチン接種や免疫グロブリン投与で対応します。妊娠前の検査で抗体がない場合はワクチンを接種し、将来の感染リスクを下げます。
C型肝炎(HCV)
特効薬で治療可能になりましたが、妊娠中の使用は制限されます。妊娠前の発見と治療が望ましいです。無症状でも感染している場合があるため、輸血歴や刺青歴がある人は特に注意が必要です。
梅毒
進行すると全身の臓器に障害を与えるだけでなく、先天梅毒として胎児に感染します。胎児死亡や重度の障害を避けるため、早期発見と治療が必須です。血液検査で簡単に判明し、ペニシリン治療で完治可能です。
クラミジア・淋菌
不妊の原因としても有名で、特にクラミジアは日本で最も多い性感染症です。感染しても自覚症状がない場合が多く、定期検査が重要です。妊娠中に感染すると早産や新生児肺炎の原因にもなります。
風疹抗体
抗体がなければワクチンを接種。妊娠初期に感染すると先天性風疹症候群のリスクが非常に高くなります。自治体によっては抗体検査やワクチンの費用助成があります。例として東京都では、妊娠希望者とそのパートナーを対象に無料クーポンを配布しています。
トキソプラズマ
猫の糞や加熱不十分な肉から感染。胎児に脳や目の障害をもたらすことがあります。IgG・IgM抗体検査で最近感染か既感染かを判断します。妊娠前に陽性が分かれば、感染時期を推定して胎児への影響を評価できます。
サイトメガロウイルス(CMV)
保育園児との接触で感染することが多く、妊娠中初感染は胎児の難聴や発達障害の原因になります。特に保育士や小さい子の親は注意が必要です。こまめな手洗いと口移しでの食事提供を避けることが予防につながります。
HPV
子宮頸がんの原因ウイルス。性交経験のある女性の多くが一度は感染します。HPVワクチンや定期的な子宮頸がん検診が有効です。妊娠前に子宮頸部異形成が見つかれば、早期治療で進行を防げます。
細菌性膣炎(BV)
膣内の善玉菌が減り、悪玉菌が増えることで起こります。早産や低出生体重児のリスクが高まります。治療には抗菌薬が用いられ、再発防止のために生活習慣の改善も行います。
3. 検査のタイミングと方法
妊活開始の3か月前までに受けるのが理想です。ワクチン接種後は2か月程度の避妊期間が必要な場合もあります。
血液検査、尿検査、膣分泌物検査でほとんどの感染症を確認できます。費用は自費だと1項目2,000~5,000円程度、パネル検査で1~3万円ほど。自治体の補助がある場合もあります。
4. パートナーと一緒に受ける理由
感染症はカップル間で再感染を繰り返すことがあります。どちらか片方だけ治療しても意味がないため、二人同時の検査が理想です。パートナーも無症状感染している可能性があり、特に男性は症状が出にくい傾向があります。
実際に、ある夫婦はクラミジア検査で夫のみ陽性が判明し、治療後に妊活を再開して無事に妊娠・出産を迎えました。このように、両者で検査を受けることでトラブルを未然に防げます。
5. 検査後の対応
陽性であれば医師の指示に従って治療を行い、妊娠時期を調整します。陰性であっても生活習慣を見直し、再感染防止に努めます。猫を飼っている場合は妊娠前からトキソプラズマ対策を徹底します。
感染症の多くは適切な治療と予防で十分対応可能です。大切なのは「知ること」。自分の体の状態を知ることで、不安を減らし、妊娠・出産への準備が整います。
6. 自治体の助成制度と活用方法
多くの自治体では、妊娠前の感染症予防や早期発見のために、抗体検査やワクチン接種の費用を助成しています。例えば東京都や神奈川県では、風疹抗体検査を無料で受けられるクーポンを配布しており、該当する場合は医療機関で自己負担なしで検査が可能です。また、一部地域ではB型肝炎ワクチンの助成も行われており、妊娠前から免疫をつけられるようになっています。助成制度は自治体ごとに異なるため、必ず市区町村のホームページで最新情報を確認しましょう。
7. 検査の所要時間と結果が出るまで
検査自体は採血や採尿、膣分泌物採取で10〜30分程度で完了します。結果は即日わかるものもあれば、数日〜1週間かかるものもあります。例えばクラミジアや淋菌の核酸検査は2〜3日、トキソプラズマや風疹抗体の結果は1週間前後が一般的です。妊活スケジュールを考慮し、結果が出る時期も見越して受けるとスムーズです。
8. 感染症予防のための日常生活アドバイス
- 手洗いの徹底:外出後や調理前後、ペットの世話後は石鹸で20秒以上洗う
- 食品の加熱:肉や魚は中心部までしっかり加熱し、生卵や生肉は避ける
- 性行為の安全対策:コンドームの使用やパートナーとの相互検査
- 口移しでの食事提供を避ける:特に小さな子どもとの接触でCMV予防に有効
- 清潔な住環境の維持:寝具や下着のこまめな洗濯、タオルの共有を避ける
これらの小さな習慣が、妊娠前の体を守る大きな力になります。感染症は一度かかると妊娠や出産に影響を及ぼすことがありますが、日常生活の工夫で多くは予防可能です。
まとめ
妊娠前の感染症検査は、母子の健康を守るための第一歩です。パートナーとともに検査を受け、必要な治療や予防策を講じることで、安心して妊娠・出産を迎えられます。
「検査は不安だから避ける」ではなく、「検査を受けるから安心できる」という発想に切り替えましょう。将来の赤ちゃんの健康は、妊娠前の一歩から始まります。