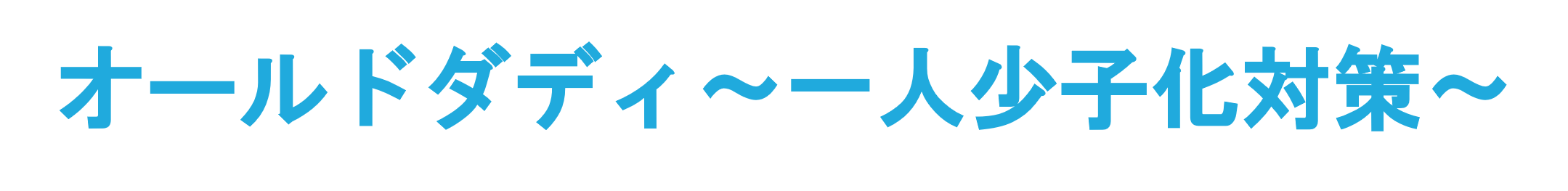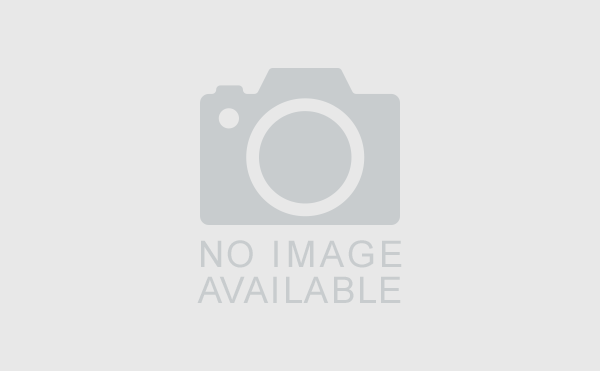FTMトランスジェンダーが「子どもを望む」とき──精子提供という選択と現代社会の課題

はじめに
FTM(Female to Male)トランスジェンダーの人々にとって、自分らしい性別で生きることは大きな一歩です。しかし、その先に「家族を持ちたい」「子どもを育てたい」という願いが生まれたとき、日本ではまだ社会や制度がその思いに十分に応えられていません。
本記事では、FTMの当事者が子どもを持ちたいと考えたときの現実、特に「精子提供」という方法に焦点を当てて、その背景、課題、当事者の声、そして今後社会に必要な変化までを深く掘り下げていきます。
FTMとは何か?
FTM(Female to Male)とは、生まれたときに割り当てられた性別が女性である一方、自認する性が男性である人を指します。FTMの人々の中には、ホルモン療法(テストステロン注射)や乳房切除手術、子宮摘出手術など、医療的措置を受ける人もいますが、それらは必須ではなく、本人の選択によって異なります。
日本では戸籍の性別を変更するために、一定の条件(未成年の子どもがいないこと、手術の実施など)が必要とされており、FTM当事者が子どもを持つという選択には複雑な事情が絡んでいます。
「子どもが欲しい」と思うのは自然なこと
性別にかかわらず、人が「子どもを持ちたい」と思うことは極めて自然な願いです。恋人やパートナーと家庭を築きたい、誰かを育てたい、血縁に限らずとも愛情を注げる存在を持ちたい──これらは性自認や性的指向に関係なく、多くの人が抱く感情です。
FTM当事者も同様に、人生のある時点で子どもを持つことを真剣に考える人が増えています。その際に浮上する現実的な手段のひとつが「精子提供を受けてパートナーが妊娠する」という選択です。
精子提供という手段とは?
精子提供とは、第三者(ドナー)から提供された精子を用いて妊娠を目指す方法です。異性愛のカップルや不妊治療においても使われる手段ですが、FTM当事者やレズビアンカップルにとっても、子どもを持つための重要な選択肢となっています。
精子提供には大きく分けて2つの方法があります。
- 精子バンクの利用 医療機関や専用機関を通じて、匿名ドナーからの精子を使用する方法。安全性や感染症リスクの低減がメリット。
- 個人提供 SNSやマッチングサイトなどで個人のドナーを見つけて直接提供を受ける方法。柔軟性がある反面、法的・健康的なリスクも高い。
FTMが精子提供を選ぶ背景
FTM当事者が精子提供を選ぶ理由には、以下のような背景があります。
● 自分が妊娠・出産することへの葛藤
性自認が男性であるFTMにとって、自身の体で妊娠・出産を経験することは、性別違和による強いストレスを伴う場合があります。ホルモン療法を中止しなければならないことも精神的・身体的な負担となります。
そのため、パートナー(多くは女性パートナー)が妊娠を担うことが多いです。実際、私にご相談いただくFTMの方はほとんどがそうです。
● 法的な障壁を乗り越える選択
日本では、FTMが戸籍変更後に子どもを持つことには制約があります。しかし、出産を担うのがパートナーである場合、FTM本人は法的には「実父」ではなくとも、生活上の“親”として子育てに関わることが可能です。
● 家族としてのつながりを築きたい
血縁の有無にかかわらず、パートナーとの間に新しい命を迎えることで、家族としての一体感が生まれます。
FTMカップルで精子提供を希望している方からのお問い合わせには血液型を気にされる方が多いと感じます。
これは精子提供だとしても夫婦と子供で血液型での繋がりを大事にしたい場合や、輸血の問題などを気にされているケースがあります。
例えば、夫がA型で妻がO型であれば、AかOのどちらかを希望する方が多いです。
精子提供のプロセス
FTM当事者が精子提供を通じてパートナーとの間に子どもを持つ場合、以下のようなステップが一般的です。
- ドナー探し
- 精子バンク(国内・海外)
- 個人提供マッチングサイト、SNSなど
- 提供形式の選択
- 医療機関での人工授精(IUI)
- 自宅でのシリンジ法
- 事前の健康チェック
- 感染症・遺伝病の検査
- 提供を受ける側(パートナー)の排卵周期確認
- 同意書や契約書の作成(可能であれば)
- 将来の法的トラブルを避けるための書面化
- 妊娠成立・出産
- 家族としての体制構築(生活・保育・戸籍の調整)
精子提供に関するメリットと課題
メリット
- パートナーとの子育てが実現できる
- 身体的・精神的負担の軽減(本人が妊娠しない場合)
- 比較的短期間で妊娠に至る可能性
- 精子バンク利用時の安全性の高さ
課題・リスク
- 日本では精子バンクの数が少なく、選択肢が限られる
- 海外精子バンク利用には高額費用が発生
- 個人提供の場合、法的保護が弱い
- ドナーとのトラブル(出自を知る権利、提供時の性被害など)
- 非出産側パートナーの親権取得が困難
当事者の声
「私はFTMで、長年パートナーと生活を共にしてきました。彼女と家族を築くために精子提供という道を選びました。私自身が妊娠することには抵抗がありましたが、彼女が出産を引き受けてくれたことで、私たちの夢が現実になりました。」
「精子提供の情報は少なく、信頼できる医療機関や支援団体を探すのが大変でした。制度の不備も多くて不安でしたが、それでも“家族をつくる”という強い気持ちが私たちを支えてくれました。」
当事者の声は、同じように悩み、考えている人たちにとって大きな励みとなります。
FTMならではの苦悩
FTMカップルで籍を入れている場合、クリニックでの精子提供が受けられないことが多いです。基本的には夫婦でしか受けられないというというクリニックが多いです。
クリニックでの人工授精は男性女性の双方が結婚していないことが条件になっているケースがあります。
レズビアンカップルの場合は結婚していないため、ドナーが協力してくれれば問題なくクリニックでの人工授精が可能ですが、
FTMカップルで籍を入れている場合は既婚者になるため、クリニックでの受診が出来ません。(私がお世話になったクリニックはそうでした)
そのため、FTMのパートナーをお持ちで子供が欲しい方は、結婚する前に詳しくパートナーとよく相談しておきましょう。
社会に求められる変化
FTMを含むLGBTQ+当事者が安心して家族を持てるようにするには、社会全体の意識改革と制度整備が必要です。
- 同性パートナーやトランスジェンダー当事者の育児・出産を支える法律の整備
- 精子バンク制度の整備と提供体制の明確化
- 医療機関へのLGBTQ+対応研修の普及
- 学校や地域社会での多様な家族モデルへの理解促進
- 当事者へのカウンセリング・情報支援の強化

まとめ
FTM当事者が「子どもを持ちたい」と願うとき、その思いは決して特別なものではなく、ごく当たり前の人間的な感情です。精子提供という方法は、その願いを現実にする一つの選択肢であり、多くの希望と可能性を秘めています。
しかし、現状では制度、情報、医療体制など、さまざまな課題が山積しています。それでも、ひとつひとつの選択が道を切り開き、当事者自身とその家族、そして社会全体にとって新しい価値観を育むきっかけとなるはずです。
年齢の問題もあり、社会の変化を待っていては子供を授かることができないという心配もあると思います。
制度の面では厳しい状況も続きますが、私も精子提供のドナーとして、FTMの皆様に養育費の提供などできることをしていきたいと思います。
ご相談いただいた皆様にはできるだけ寄り添った提案をしていきたいと思っていますので、精子提供についてお考えの際は是非お力添えさせてください。